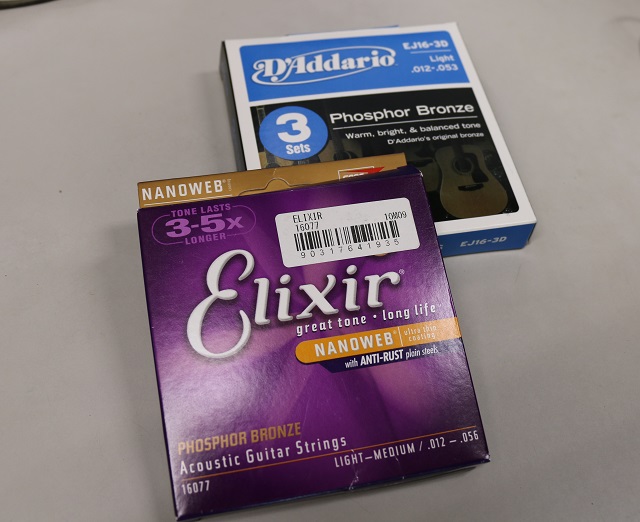毛皮の褪色・変色(赤の褪色の証し)
今日は、何回か書いている毛皮の褪色について、もうひとつ書いてみます。以前から褪色は赤から始まると書いてありますが、今回の写真がそのいい例ですね。写真は一番褪色しやすい肩の部分です。
コートの色はイエローを少しくすませた色です。写真を見てもらえばわかりますが、ほとんど変化がありません。
その理由はイエローの構成色に赤がないからです。当社アトリエのHPににもグリーンの刺し毛ミンクのマントの写真がありますが、このマントもほとんど褪色しませんでした。やはりグリーンはイエローとブルーが構成色なので、赤が存在しなく、変色はしません。 (さらに…)